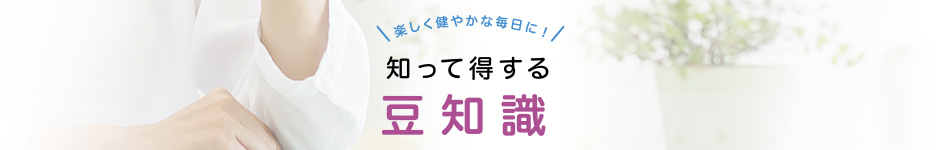
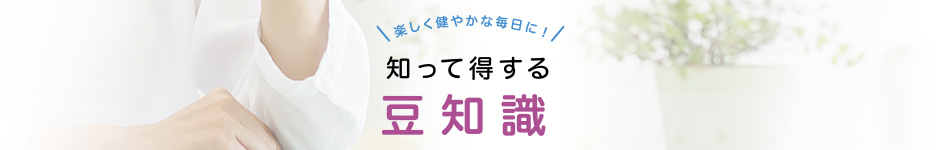
今井眞一郎教授インタビュー・後編
2023年7月6日
「走ると息切れをするようになってきた」「人に会ったり外出したりするのが億劫になってきた」--。 病気ではないけれど、心と体が弱ってきて介護が必要な状態になりやすい、健康と要介護の間の虚弱な状態を示す「フレイル」。人生100年時代と言われる今、その予防は多くの人にとって関心事の一つではないでしょうか? そんな中、ワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)教授によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来 人生100年時代へのソリューションを探る」が5月11日にリアルとオンラインで開催されました。 今井教授と言えば、36年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見。国内はもとより世界中で注目されています。 フレイルとNMNの関係は? 超高齢化社会に突入している日本がやるべきことは? 前後編にわたってお話を伺いました。 ※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種 --今井教授はワシントン大学で研究をされていますが、アメリカと日本を行き来しているからこそ気づくことがあると思います。後編では「超高齢化社会に突入している日本社会が取り組んでいかなければいけないこと」をテーマにお話を伺えればと思います。 今井眞一郎教授(以下、今井):今の日本を見渡すと、外国からの観光客がすごく多いことに気づくと思います。それ自体は素晴らしいことだとは思うのですが、時々報道されている通り、背景に日本の物価の破格な安さがあります。物価が安くて外から人が来て経済が回っても、それが賃金に反映されていないのが問題だと考えています。 日本の社会は超高齢化社会になっていくのは誰の目にも明らかなのですが、国民の健康を保とうとベンチャー企業を作って薬を作ろうという動きもあります。でも、薬を開発するコストは高くなるばかりですし、薬を手に入れるには医師からの処方箋が必要なので、このままですと限られた人たちにしか薬が行き渡らないという現実があります。 そのために、前回のインタビューでもお伝えしたとおり、臨床治験でその機能や効能が確実に実証された、生体が持つNMNのような物質がオーバーザカウンターで(薬局やドラッグストアなどで処方せんなしに購入できる製品として)手軽に手頃な価格で買えることが必要です。このような生体物質は、ニュートラシューティカルと呼ばれています。 NMNも高品質なものは確かにまだ高いです。ただ、原資の価格がかなり落ちてきています。ですから、確実に効果が証明されたものが手頃な価格で多くの人に行き渡るようになるのは、時間の問題であろう、と考えています。 --いくら良い製品であってもごく限られた人しか手に入れられない状態では意味がないのですね。 今井:それでは反発しか起こらないし、そんな国にしてはいけないと思います。この技術を応用していく際に、できる限り多くの人たちに行き渡る努力をしないといけない。確かに開発したばかりのニュートラシューティカルは高いです。なので、同時に普及させる努力も必要です。おかげさまでNMNは本当に効果があると広く浸透してきた手応えを感じていますが、今後はいかに正しく使えるか? どういう効能があるから使えるか? ということを正しく知らせることが大事になってくると思います。いかに多くの人がサステナブルに使える仕組みを作ることが大事です。 --NMNの正しい摂取の仕方を伝えることもメーカーやメディアの責任ですね。 今井:そうです。前回もセミナーでお話ししたことですが、「NMN点滴療法」の危険性については繰り返しお伝えしたいです。血中に高濃度のNMNを直接点滴すると、SARM1(NMNの濃度が上がると活性化されて、NADを破壊してしまう酵素)が不必要に活性化されてしまう可能性が十分に考えられます。今回お話しした内容からも、重要な神経細胞の働きを刺激し過ぎてしまう可能性があるという意味でもやはり勧められないです。 NMNの正しい摂取という意味では、NMNを飲むタイミングも午前から昼間が良いです。特定の神経細胞を決まった時間に刺激することが大事で、本来刺激してはいけない時間に刺激するのはお勧めできません。例えば筋肉を休ませる夜の時間帯にNMNをとるのはやめたほうが良いです。また、NMNの量も多ければいい、というものではありません。最近はやたらに大量のNMNを入れた製品が出回っていますが、多く取ればいいというものではないことを知っておくのも大切なことです。 --研究の領域で感じていることや危機感はありますか? 今井:サイエンスで言えば、研究者というのは海外の学会にどんどん出かけて、最先端の結果に触れていないといけないのですが、経済的な事情もあって、日本では十分なサポート体制が用意できていないというのは大きな問題と考えています。特にコロナ禍の3年でさらに日本のガラパゴス化が進みました。 --例えばコロナ禍でライフスタイルも変わりました。今まで会議と言えば対面が当たり前だったけれど、コロナ禍をきっかけにオンライン会議も当たり前になりました。それでもやはり外に出かけて行ったり、直接人と会うことは大事でしょうか? 今井:やはり人と人のインタラクション(触れ合い)を軽く見てはダメだと思います。重要な情報は相手の表情や身振りを見ながら話すと言うのが生物学的にも大事です。マスクをしたままで顔の下を隠してコミュニケーションをとるのは難しいことをみなさん痛感していると思うのですが、ヒューマンインタラクションをとって大切な話をするのはサイエンスも一緒です。日本も早く正常な社会活動ができる状態に戻ってほしいです。世界の流れに目を向けた活動を促進する努力をしないと、どんどんガラパゴスになるという意味で危機感を感じています。 --貴重なお話をありがとうございました。最後に記事を読んでいるみなさんにメッセージをお願いします。 今井:不確かな情報に惑わされないように、正しい情報をフォローアップしてご自分の健康や長く生きていく人生を考えてほしいですね。せっかく抗老化技術が手に入るようになってきているのに、自分たちの世代や自分のことだけを考えていては、社会の格差は開き分断は進むばかりです。 新しい技術を応用して元気になった人たちには次の世代のことを考えて知識や経験を分け与える良識が求められます。社会全体が良い方向に進むように知恵を絞り、モチベーションを高めていくことが、人生100年時代を生きる私たちの義務であるし使命だと考えています。
「確実に実証された抗老化物質を誰もが手にできる社会に」今井教授が目指すもの
「正しい摂取の仕方を伝える」新しい技術の開発と同時に大切なこと
コロナ禍で進んだ日本のガラパゴス化