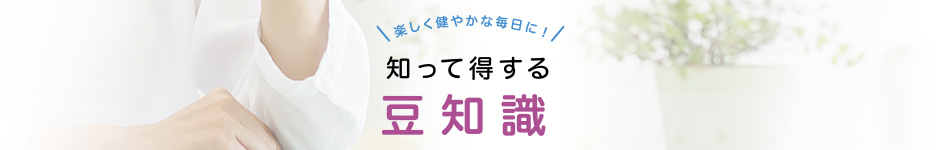
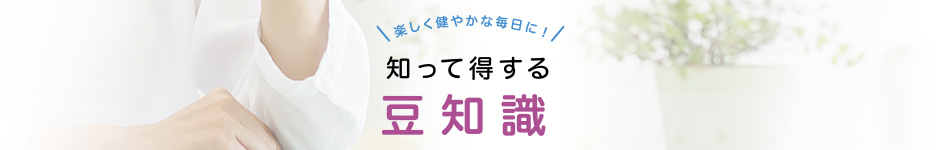
今井眞一郎テオドール&バーサ・ブライアン卓越教授インタビュー・前編
2024年7月9日

37年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見したワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)テオドール&バーサ・ブライアン卓越教授(環境医学)(以下、今井卓越教授)によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来」が2024年6月3日に東京都内で開催されました。
今回で4回目を迎えるセミナーのテーマは「抗老化科学を生かした活力ある生活のビジョン」。セミナーでは、老化・寿命研究について、これまでに明らかになっている科学的知見をどんなふうに日々の生活の中に生かしていくかについて講演した今井卓越教授にお話を聞きました。
※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種。
––––「朝食をしっかりと食べてサーカディアンリズムを整えましょう」というのは、すぐにでも実践できますね。セミナーでも詳しくお話されていましたが、注意点などあるのでしょうか?
今井眞一郎卓越教授(以下、今井):「間欠的断食」という言葉は聞いたことがあるでしょうか? 英語では「インターミッテントファスティング」と言いますが、世の中でも流行ってきています。確かに効果はあるのですが、実践している方にお話を聞いてみると、多くの方々が朝食を抜いているんですね。
例えば、朝食や昼食を抜いて夜は家族と普通に夕食を食べる。それではおそらく効果は薄いでしょう。なぜかと言いますと、講演でもお話したように、夜の時間帯はカロリーをできるだけとらないようにして、就寝中の血糖値がそれほど高くならないようにするのが非常に大事だからです。
何を食べるかよりいつ食べるか––––。時間制限食と言って、サッチダナンダ・パンダ博士(米ソーク生物学研究所教授)という研究者がマウスやヒトで研究を進めていらっしゃいます。食事をとる時間を8時間から10時間に抑えるのですが、体重減少に加えて、糖尿病や高血圧、高脂血症といった疾患を改善するのに効果があるということも分かっています。動物実験のレベルではアルツハイマー病や睡眠障害を改善することも分かってきています。老化に関して言えば、老化を遅延させるのに効果があると言われています。
要は、活動しているときに食事をとるのは問題ないのですが、本来の活動期ではない時間帯に食べるのが良くないということなのです。マウスの場合でも、活動している時間帯に食べる分には太って代謝に異常が出る、ということは少なくとも起こりません。マウスの実験でも、夜行性のマウスに夜間に高脂肪食を与える分には太らないし、糖尿病にもならないのですが、昼間にそのような食事を与えるとぶくぶく太って糖尿病になってしまいます。
NAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド/生命活動に必須の物質)はエネルギーの産生に欠かせませんが、各種の臓器におけるNADの量はサーカディアンリズムを刻んで変動しています。マウスの場合は夜に、ヒトの場合は昼に高くなります。そのためには朝食をしっかり食べてサーカディアンリズムを整えることが大事なのですが、残念なことに、老化でNADがどんどん減少してきてしまうことが分かっています。NADの量の振り幅が小さくなってしまう。それを若い頃の状態に戻すために、NMNを与えるというわけです。

––––いわゆる「NADブースティング」ですね。
今井:そうです。全身でのNADの減少を防ぐために、NADの合成に必要となる物質を投与することで、NADの量を上げてやろうという方法です。そのために使われる物質がNMNです。例えば、お年を召してきた方が朝食を食べた上で、NMNを朝から午前中に飲むことで、NADの振幅を元に戻しNADのリズムを正常に保つことができるようになる。それを毎日のように繰り返すことで、抗老化の方向に働く、というわけです。
NMNの投与の仕方についてですが、これはとても重要なことなので、毎回お伝えするのですが、マウスの実験でNMNを直接体内に入れると、血中のNMNの濃度が相当高い濃度に達します。このため体内に直接NMNを投与するとSARM1(NMNの濃度が上がると活性化されて、NADを破壊してしまう酵素)が不必要に活性化されてしまう可能性があります。なので、長期的に神経障害を引き起こす可能性が懸念されます。
––––美容情報としてNMNの点滴が推奨されている記事を見たことがあります。
今井:科学的な根拠はゼロです。絶対に点滴投与はしないでください。また、「では経口ならいいのか?」という話なのですが、大量のNMNを一度に経口摂取すると、血中のニコチンアミドが高濃度に達します。ニコチンアミドの長期過剰摂取は肝機能障害を生じさせる可能性があります。少なくとも臨床試験で安全性が確保されている量が一日250~300ミリグラムです。1回の投与での安全性で言えば、500ミリグラムが最大です。