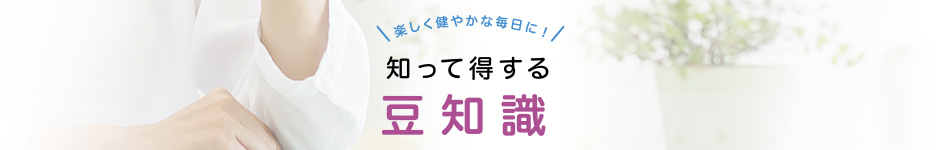
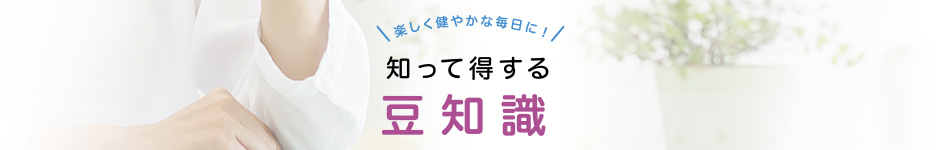
今井眞一郎卓越教授インタビュー・前編
2024年2月1日
36年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引してきた、ワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう )卓越教授。2023年8月にはワシントン大学から、テオドール&バーサ・ブライアン卓越教授(環境医学)の称号※を授与され、その研究に世界から熱い視線が注がれています。 このたび、「臓器間コミュニケーション」に関する重要な発見に関する論文を発表した今井卓越教授にお話を伺いました。前後編。 --昨年12月に東京都内で開催されたセミナーでも「視床下部背内側核(DMH)に存在する特定の神経細胞群が、視床下部と白色脂肪組織の間でコミュニケーションをし、eNAMPTの分泌を促し、老化と寿命を制御していることが明らかになった」と発表されていました。今回、発表された研究内容のポイントを詳しくお聞かせください。 今井眞一郎卓越教授(以下、今井):視床下部の特定の場所「DMH」にある特別な「Ppp1r17神経細胞」を新たに同定し、この神経細胞が白色脂肪とコミュニケーションを取ることによって脂肪組織の機能を保ち、それによって老化・寿命の制御に重要な役割を果たしていることが分かりました。 特に今回、老齢マウスにおいてPpp1r17神経細胞に遺伝学的な操作を行い、神経細胞の働きを活性化したところ、eNAMPTの分泌が亢進し、マウスの老化が有意に遅れ、寿命が延長しました。 これは、Ppp1r17神経細胞を刺激すると、脂肪組織の中に張り巡らされている交感神経系を通じてeNAMPT (細胞外に分泌されるNAMPT)が分泌されることによって起こります。eNAMPTはNAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド/生命活動に必須の物質)の合成に重要な酵素であり、これがDMHにいってNADを上昇させて神経細胞を活性化するフィードバックループができている、と考えられます。 視床下部のPpp1r17神経細胞と脂肪組織のフィードバックを保つこと、それが今回のテーマの「臓器間コミュニケーションを高めて老化・長寿を実現する」ということになります。 NMNでも、DMHのNADは高まります。一方で、NMNを作り出す酵素・eNAMPTを高めてもDMHのNADが高まることがわかっています。 --eNAMPTを高めるというのは? 今井:例えば、まず運動です。運動すると骨格筋の中のNAMPTの量、また血中のeNAMPTの量が増えます。ヒトでもマウスでも増えます。運動は明らかにeNAMPTを増やす効果があります。ただ、運動は健康寿命を伸ばす効果はあるのですが、絶対寿命を伸ばす効果はありません。運動することでフィードバックループがうまく回るようになるのですが、そのループを働かせ続けるには、おそらく別の神経細胞を健康に保つ努力が必要です。仮説ですがNMNはそういう働きを持っている可能性があると思っています。NMNは脳の中枢で重要な働きをしていると考えられますが、まだ研究の段階です。次の機会くらいに、NMNが脳の中でどんなことをしているかが発表できるかもしれません。 --若いマウスからeNAMPTを含んでいる細胞外小胞を取り出して(eNAMPT内包EV)老齢マウスに注射すると、抗老化作用が認められて寿命も伸びるというお話もあり、ヒトへの応用も数年のうちには実現するだろうということでしたね。 今井:年を重ねていくうちに血中のeNAMPTの量が減るから補充する、という考え方です。ヒトの場合は、ご本人の血液を頂いて、そこから血漿を分離してeNAMPT内包EVを精製し、凍結保存しておく。それを半年後や数年後に本人に戻してやる、という方法(eNAMPT-EV Therapy; eNET)を考えています。それに関しては、非常に新しい技術を導入することでeNAMPT内包EVを安全に、高精度で分離する研究が必要です。 --例えば、30歳の時のeNAMPT内包EVを取っておいて50歳になったら戻すということも可能なのでしょうか? 今井:可能です。eNAMPT内包EVは凍結保存で安定なので、決して夢の話ではないと思います。また興味深いことに、NMNとeNAMPT内包EVを与えた時の効果は完全に一緒ではありません。 --どういうことでしょうか? 今井:NMNを与えると肝臓や視床下部でNADが上がるのですが、eNAMPT内包EVを与えても肝臓では上がらず、視床下部で上がるんです。組織特異性と言って、どの組織で働くかが決まっているようなのです。 もう一つ、NMNをどんどん与えるとNADになって、NADが使われると壊されてニコチンアミドに変化し、溜まります。ニコチンアミドを再利用してNMNに作り直すのにはNAMPTが必要となります。だから、両方を与えるとダブルの効果が出るはずという考え方です。それも数年のうちに実現されるのではないかと考えています。 ※Distinguished Professor(卓越教授)の称号は、米国の大学において非常に功績のあった、優れた業績をもつごく少数の教授にのみ与えられ、大学に対して大きな貢献のあった個人あるいは家族の名前が冠せられるのが慣習となっている。今回は、今井教授の長年にわたる老化・寿命研究分野での業績が評価され、地球環境に大きな貢献をもたらす医学研究である、ということから当称号が授与された。
視床下部の特別な神経細胞を同定…明らかになった臓器間コミュニケーション
ヒトへの応用は? 自身のeNAMPTを用いる療法の開発が進行中
https://www.irpa.ne.jp/newsより引用