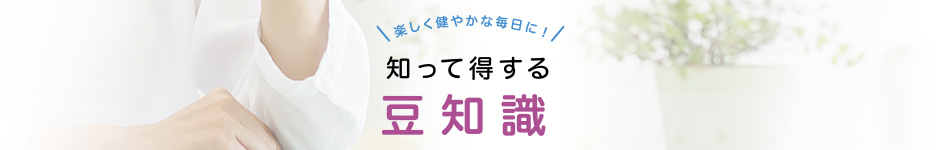
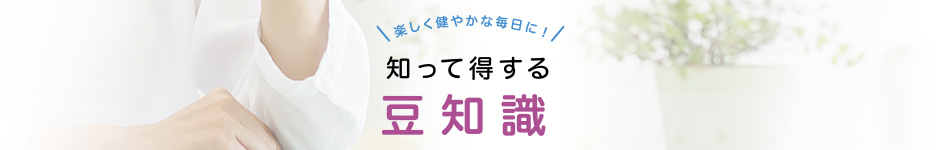
今井卓越教授「臓器間コミュニケーションを高めて健康長寿を実現する」セミナー・前編
2024年2月1日
36年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見したワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)卓越教授によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来 臓器間コミュニケーションを高めて健康長寿を実現する」が2023年12月4日に東京都内で開催された。 今回で3回目を迎えるセミナーのテーマは「臓器間コミュニケーション」。今井卓越教授によると「脳の奥深くにある『視床下部』と『脂肪組織』や『骨格筋』とのコミュニケーションが、老化と寿命の制御に重要な働きをしていること、そしてNMNがこうしたコミュニケーションを支え、重要な働きをしていることがわかってきた」という。 臓器間コミュニケーションとは何なのか? セミナーの模様を前後編でお届けする。 ※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種。 セミナーの模様 老化・寿命研究の分野では、加齢に伴うNAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)の減少によってさまざまな臓器の機能が低下し、老化に関連する疾患を引き起こす原因となっていることが突き止められている。 NADは、すべての生物が生命を営む上で必須の物質だ。多くの酵素反応に関わり、老化や寿命の制御に重要な役割を果たしている酵素「サーチュイン」(哺乳類には7種類ある)を活性化する。 特にNADの合成中間体であるNMNを摂取することで、加齢によって減少したNADを補充することができる。NMNが抗老化物質として注目を浴びているゆえんだ。 ここ10年近くの研究によって、「視床下部が哺乳類の老化・寿命制御のコントロールセンター(司令塔)として機能している」ということがわかってきた。 視床下部は、体の「司令塔」と言える部分で、脳の奥深くにある。私たちの体が正常に機能するために、例えば摂食行動や睡眠、さまざまなホルモンの分泌などをコントロールしている。また、私たちの体には自律神経が張りめぐらされていて、体温や心臓の動き、血管の働きなどを細かく調節しているが、自律神経を調節しているのも視床下部だ。 今井卓越教授のグループは、視床下部の特定の領域でサーチュインの働きを強めると、マウスの老化が遅れて長寿になることを明らかにした。そして、サーチュインの中でもSIRT1と呼ばれるサーチュインが視床下部で老化と寿命の制御のために重要な働きをすることがわかった。そして、SIRT1が働き続けるためにはNADを常に必要としている。 では、NADは何によって支えられているのだろうか? 実は視床下部のNADは脂肪組織によって支えられていることがわかった。脂肪組織は、SIRT1とNAD合成に必須な酵素NAMPT(ニコチンアミド・ホスホリボシルトランスフェラーゼ/NMNを作る酵素)を血液中に分泌する。NAMPTは「細胞外小胞」と呼ばれる小さな粒の中に封じ込まれて血中に分泌され(eNAMPTと呼ばれる)、視床下部に到達するとeNAMPTは細胞の中に送り込まれて、NMNやNADの産生が行われる。 マウスでもヒトでも血中を巡っているeNAMPTの量は老化と共に減少するが、マウスではeNAMPTの量を測ることでそれぞれのマウスの個体の余命があとどのくらいあるのかを、かなりの精度で予測することができるという。また、若い個体からeNAMPTを含む細胞外小胞を取り出し、老齢個体に注射すると顕著な抗老化作用が認められ、寿命も顕著に延長することがわかった。つまり、脂肪組織が分泌しているeNAMPTが哺乳類における老化と寿命の制御に重要な役割を果たしている、ということが明らかになっていた。 そして今回のセミナーでは、上述した脂肪組織からのeNAMPTの分泌が「Ppp1r17神経細胞」という特別な神経細胞群によって、制御されていることが明らかになった、と発表された。今井卓越教授は、この「Ppp1r17神経細胞」の同定に約10年の月日を要したという。 「Ppp1r17神経細胞」は視床下部の特別な場所(視床下部背内側核)に存在しており、交感神経を介して脂肪組織へと刺激を伝達する。それに応答して、脂肪組織からはeNAMPTが放出され、血流に乗って、視床下部を含む標的の臓器に到着する。そして細胞内にeNAMPTが送り込まれることで、NMNやNADの産生が行われるのだ。つまり、「Ppp1r17神経細胞」を介して、視床下部と脂肪組織の間でコミュニケーションが行われ、老化と寿命を制御していることが明らかとなったのだ。 このコミュニケーションの重要性はマウスでの実験で確認されている。例えば若齢マウスの視床下部でPpp1r17の量を下げると、身体活動量が落ちて観覧車を回せなくなってしまう。また脂肪分解が抑制され太ってしまう。これは「Ppp1r17神経細胞」の機能を下げることで白色脂肪組織に張りめぐらされている交換神経系が減退し、脂肪組織が制御を受けられないからだ。反対に、老齢マウスで「Ppp1r17神経細胞」を活性化させると身体活動量が増え、白色脂肪組織の機能が上昇する。それによって、eNAMPTの分泌が促され、老化に伴う死亡率が有意に減少し、寿命が延長する。 今井卓越教授はこの研究結果について「人為的にある特定の神経細胞を操作することで哺乳類の老化を遅らせ、寿命を延ばせた最初の例です」と語った。 骨格筋と神経細胞との臓器間コミュニケーションに関する研究も進行中だ。 「NMNを取り込む仕組みをもった視床下部の神経細胞によって骨格筋が刺激されると、特別なホルモンのような物質が分泌されることがわかってきました。私たちはこの物質が抗老化ホルモンのような形で働いているのでは、と疑っています。こうした成果を組み合わせて、数年のうちに抗老化のための人為的操作の方法が解明されていくでしょう。そうすると、抗老化の方法の実現はサイエンスフィクションではなく、いかに科学的に厳密に応用するかのフェーズに移ってくるだろうと考えています」(今井卓越教授)

NMNが注目されている理由は? 老化•寿命制御の仕組み
老化との関係は? 視床下部の重要な役割
老化と寿命を制御する脂肪組織の働き
視床下部と白色脂肪組織の間のコミュニケーション
骨格筋と神経細胞の間のコミュニケーション