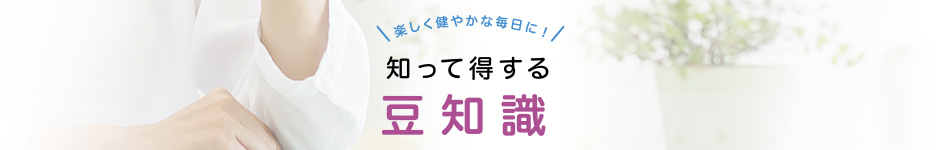
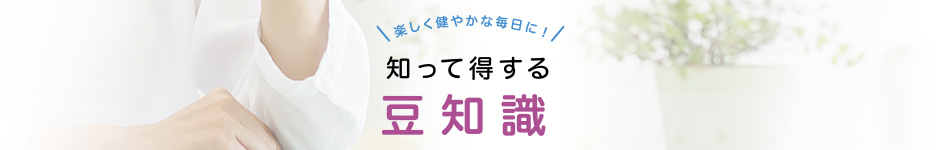
今井眞一郎教授インタビュー・前編
2023年7月6日
「走ると息切れをするようになってきた」「人に会ったり外出したりするのが億劫になってきた」--。 病気ではないけれど、心と体が弱ってきて介護が必要な状態になりやすい、健康と要介護の間の虚弱な状態を示す「フレイル」。人生100年時代と言われる今、その予防は多くの人にとって関心事の一つではないでしょうか? そんな中、ワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)教授によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来 人生100年時代へのソリューションを探る」が5月11日にリアルとオンラインで開催されました。 今井教授と言えば、36年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見。国内はもとより世界中で注目されています。 フレイルとNMNの関係は? 超高齢化社会に突入している日本がやるべきことは? 前後編にわたってお話を伺いました。 ※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種 --2022年11月に開催されたセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来 老化・寿命研究の最前線」ではNMNに関する最新の研究結果が披露されました。今回もみなさんとても楽しみにしていると思うのですが、いち早く日本のみなさんにお伝えしたい研究結果がございましたら教えてください。 今井眞一郎教授(以下、今井):今回は「フレイル」をテーマにお話をしようと思います。フレイルという言葉自体はみなさん一度は目にしたり耳にしたりしているのではないでしょうか。フレイルには身体的フレイル、精神的フレイル、社会的フレイルの三つがあり、お互いがリンクしています。 まず身体的フレイルですが、加齢に伴う筋肉量の減少と筋力の低下を指す「サルコペニア」は身体的フレイルの状態として重要視されています。なぜサルコペニアになるのかはいろいろ研究されていますが、筋肉そのものに原因を求める研究が多いです。 今回、私たちが明らかにしたのは脳の外側視床下部という領域における機能低下がフレイル・サルコペニアを引き起こす中枢性の一因であるということです。 --どういうことでしょうか? 今井:NMNを細胞外から取り込むトランスポーターというタンパク質を持っている神経細胞が脳の外側視床下部にあるのですが、若齢マウスで遺伝学的な方法でそのタンパク質の量を抑制したところ、骨格筋の筋量や筋力が落ち、走れる距離も半分くらいになってしまい、フレイル・サルコペニアの症状が見られました。逆に、老齢マウスで外側視床下部のトランスポーターの量を上げると、逆にフレイル・サルコペニアの症状が改善されました。 つまり、外側視床下部におけるトランスポーターが全身性の代謝や骨格筋機能にとって重要な働きを持っていること、骨格筋の老化に中枢性の機能低下が関わっていること、そして外側視床下部におけるトランスポーターを活性化することで、フレイル・サルコペニアの病態の少なくとも一部を改善できる可能性が示されたのです。NMNを与えると、トランスポーターを通じてそれらの神経細胞に取り込まれ、筋肉の量や機能を若い状態に保つために重要な働きをしていることがわかりました。 サルコペニアの治療法としては食事療法や運動療法が知られていますが、その効果は限定的でした。おそらく、いくら筋肉を鍛えようとしても、脳の神経細胞から「筋肉を保て」という信号がないとダメなのだろう、と考えられます。サルコペニアの重要な原因の一つに中枢性の機能低下がある、とわかったわけです。 今、トランスポーターの活性化剤の研究がワシントン大学で進んでいます。NMNと一緒にトランスポーターの活性化剤を入れて神経細胞の活動を高めることで、フレイル・サルコペニアを予防したり改善したりできると考えています。 --高齢で軽い鬱状態になる精神的フレイルや社会とのつながりが希薄化することで生じる社会的フレイルについてはいかがでしょうか? 今井:精神的フレイルや社会的フレイルに関してもマウスの興味深い実験があります。詳しくは講演でお話ししますが、精神的・社会的フレイルというのは、要はモチベーションに関わってくることです。 私たちの研究から、マウスも老化すると明らかにモチベーションが落ちることがわかってきました。マウスは5、6匹で群れで生活するのが好きなのですが、「社会的隔離」と言って強制的に1匹だけに引き離すと鬱っぽくなります。若いマウスもそうですが、老齢マウスも社会的隔離をするとモチベーションが下がる。社会的なインタラクション(触れ合い)がいかに大事か、ということを示しています。 では、なぜモチベーションが下がるのかというと、脳に腹側被蓋野(VTA)という領域があるのですが、ここの神経細胞の機能を保つための特別なタンパク質(脳由来神経栄養因子・BDNF)が落ちてしまうことが分かりました。BDNFの量が落ちることで腹側被蓋野の神経細胞の働きが落ちます。実際に若いマウスで腹側被蓋野のBDNFの量を遺伝操作的に落とすとモチベーションが落ちてしまいます。精神的・社会的フレイルを改善するためには脳の特定の働きを保たなければいけないということだと解釈しています。 --NMNとフレイルの関係についてはいかがでしょうか? 今井:脳でサーチュインの一つ、SIRT1(サーチュイン遺伝子から作られるタンパク質)の働きを高めたマウスは観覧車を回す活動がアップします。また、前回のセミナーでもご紹介した通り、脂肪組織から分泌されて視床下部のNAD(ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド/生命活動に必須の物質)を保っているeNAMPT(細胞外に分泌されるNAMPT)を生成したものを老齢マウスに与えると、観覧車を回す回数がアップします。「観覧車の活動がアップする=モチベーション」とするならば、NADを強めてサーチュインの働きを強めることでモチベーションが上がると予想されます。 ということは、NMNを与えて脳の各所の神経細胞の働きを保つことによって、フレイルを予防したり改善したりできる、と予想されます。さらに、トランスポーターの活性剤を組み合わせることでその働きがアップすると予想されるわけです。 フレイルの問題の背景にはNADの供給がうまくいかない、もしくは下がるためにサーチュインの働きが下がってフレイルという状態になるのでは、という仮説が成り立ちます。ヒトでも実証する必要がありますが、ちょっと前に東大の糖尿病内科のグループや阪大のグループがNMNの臨床治験の結果を発表しました。 まだ更なる確認が必要ですが、歩くスピードが上がったり、フレイルの改善とまではいかなくてもそういう方向を示唆する効果が見られたという報告もあります。今後も詳しく調べていくとNMNがフレイルの改善に有用と分かってくるかもしれないですね。 --フレイルの予防や改善にNMNが有用である可能性が高いというのは、日本をはじめ超高齢化社会に突入している多くの国にとっては希望ですね。 今井:老老介護や介護離職の問題など、介護は超高齢化社会を迎える、あるいはすでに迎えている私たちにとって深刻な課題です。介護状態にならない健康状態に保つだけでも大きな意味があると思います。 今回の講演のテーマの副題に「人生100年時代へのソリューションを探る」と付けました。まだソリューションは見つかったわけではないですが、まさに探っている最中で「こうしたら良いのでは?」という結果が見えつつあるのが今、ということになります。
フレイルの原因は? 脳の神経細胞とのかかわり
モチベーションの持続にも脳の働きが関係?
NMNとフレイルの関係は?